栃木県料理教室20年 温活料理教室のあおきえみこです。
今回は本当に美味しい郷土料理のしもつかれの作り方をお伝えしたいと思います。
郷土料理のしもつかれですが家庭によって様々で作り方があり
作り方を誤ると苦手な食べ物になってしまうという食の一つです。
実は地元でも苦手の料理の一つ今回は郷土料理を美味しく食べられる様に料理のコツをお伝え致します。

今回は栃木郷土食
【しもつかれ】についてお話ししていきたいと思います。
Contents 目次
しもつかれとは
「2月最初の午(うま)の日に、わらをたばねて八の字に作った「わらづと」に入れて、
赤飯といっしょに稲荷神社(いなりじんじゃ)にそなえる行事食です。
穀物の豊作を願って神さまにお供えしたのが起源」です。
2022年は2月10日
私もお嫁に来た時に義父に教えてもらい神社にお供えに行きました。
昔は神社に行くと各家庭のしもつかれがあげられており、
7件のしもつかれを食べると風邪をひかないといわれ
無病息災を願っていたとも伝えられています。
しもつかれの材料
材料は正月に食べて残ったサケの頭、節分でまいた大豆、
油揚げ、酒を搾った後の酒かす、大根と人参。
しもつかれの栄養価は
栄養価では鮭!鮭はとても体を温めてくれる食材です。
寒い冬に鮭の頭を骨が柔らかくなるまで煮込んで全て食べますので、
代謝に必要なカルシウムも豊富!
ビタミンDや(カルシュウムの吸収を助けてくれる)
ビタミンB12(赤血球の生成を助けるため、貧血予防効果)
人参のビタミンA(目や皮膚の健康を維持する働き)
大根のビタミンC (風邪予防、美肌効果)
大豆に油揚げと畑のお肉と言われる、たんぱく質も豊富。
そして酒粕
「ビタミンB群」が肌の
代謝を高め、ターンオーバーを促進。
しもつかれスーパーフードでないですか。
昔の人は寒い時こんなスーパーフード!
産み出していたのですね。
栃木県でのスーパーフード
家庭によって作り方は様々ですが
私が伝えてもらった本当においしいレシピをお伝えいたします。
しもつかれの作り方
本当に美味しいしもつかれの作り方は
動画はこちらから
美味しいと美味しくないに大きく分かれるのもしもつかれの特徴!
家庭によって作り方はそれぞれですが
シンプルなので好き嫌いが大きく分かれます。
地元の伝えてくれた伝統のおばあちゃんの作り方です。
今回は時間と手間をかけて
本当に美味しい、しもつかれ作ってみましょう。
【材料】
鮭(基本的には新巻鮭)の頭 4匹分
大根…1本
にんじん…2本
大豆(炒っておく)…2カップ
油揚げ…3枚
酒粕…400g
【作り方】
①鮭の頭に熱湯に通して洗い臭みを取り、水でよく洗う。
②湯通しした①を土鍋に入れ、たっぷりの水を加え、ふたをしないで2日間骨が柔らかくなるまで煮込む。
ふたをしない事によって魚の臭みを飛ばしてくれます。
③大根とにんじんを「鬼おろし」ですりおろし、鍋に入れる。
④炒った大豆と1cm角くらいに刻んだ油揚げを鍋に加える。
⑤鍋の中で全体が均一になるよう混ぜ、水が足りない様だったら水を足し蓋をして、弱火で3~4時間以上、大豆が柔らかくなるまで煮る。
焦げ付かないように、ときどき鍋底をかき回しながら、水を足して煮る。
⑥最後に酒粕を入れてよく混ぜ、さらに1時間煮てできあがり。味をみて、塩気が足りないようなら塩を足す。
⑦冷めて3日間くらい経つと食べ頃です。
作ってすぐは酒粕の味が立って味が馴染んでいなく、美味しくありません。
冷蔵庫で寝かす事によって美味しくなりますよ。
温活ライン登録
温活情報
教室情報をいち早く発信しています。




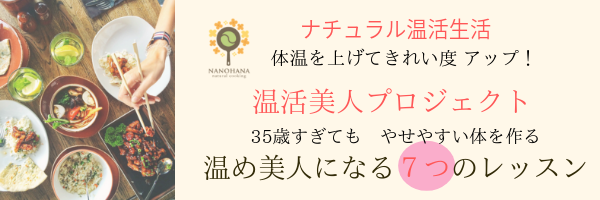



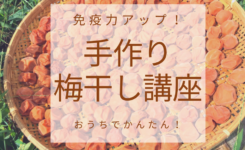


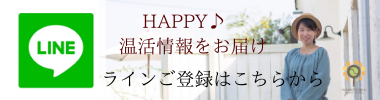














この記事へのトラックバックはありません。